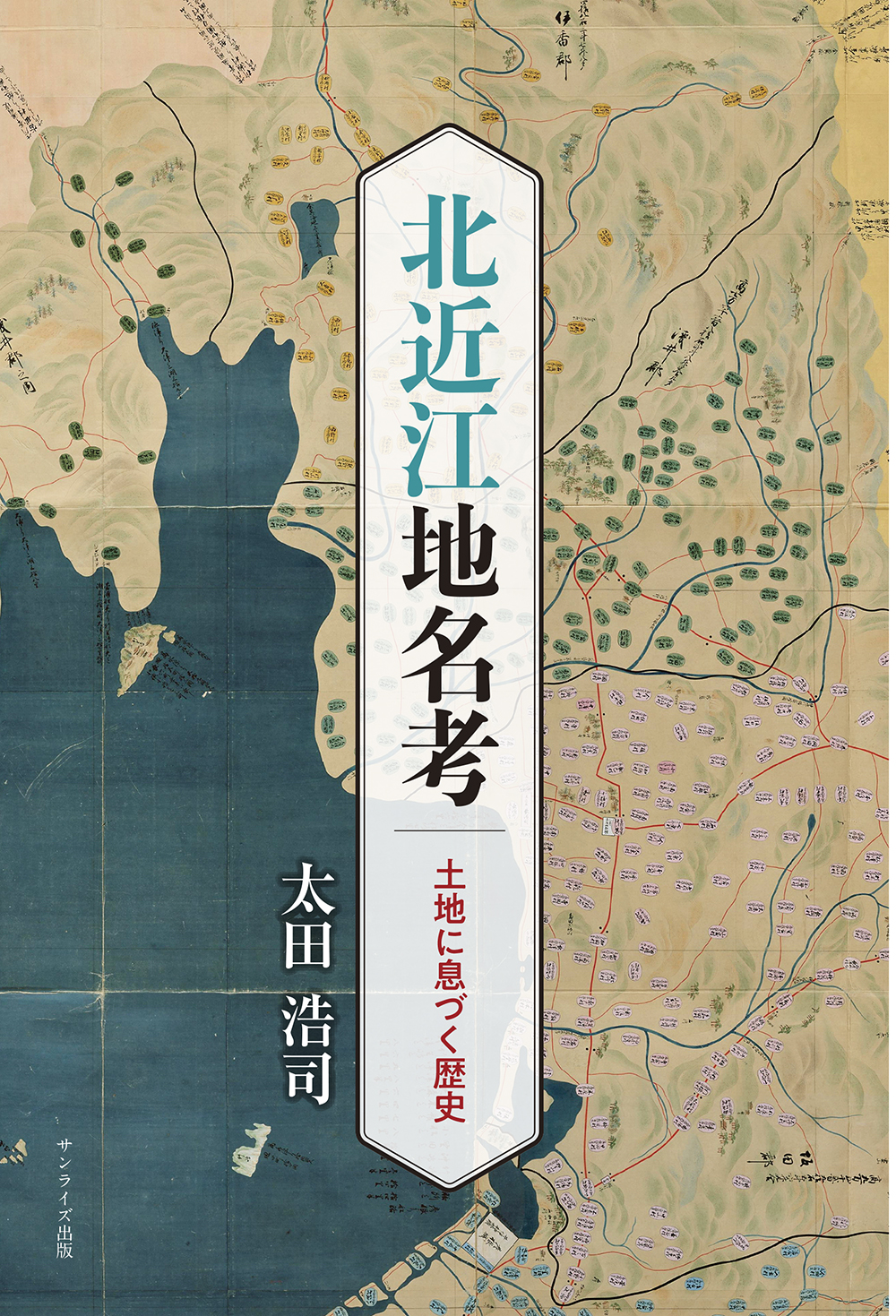
北近江地名考 土地に息づく歴史
太田 浩司
四六
212
ページ
並製
ISBN 9784883257584 Cコード 21
刊行年月日:不明
書店販売日:2022年3月14日
本体価格:1800
円
税込価格:1,980
購入する
円
内容紹介
「地名は生き物だ」ということを、我々は忘れがちである。(「はじめに」より)
領主が使う呼び名から村人が使う呼び名へ変化したらしい荘園地名、上・下、東・西のつく地名、馬がいたとは限らない「馬場」、「地名が先か・人名が先か」問題、国宝「菅浦文書」に現れる地名を追うことで見えてきた土地利用の変化──。
中世から現代に至るまでの変遷を追うと、地名は必ずその指し示す範囲が人間の必要に応じて変化していることがわかる。平成の大合併で多くの歴史的地名が失われたことに危機感を抱いた著者が、北近江三郡(長浜市・米原市と彦根市北部)の荘園名、大字名、小字名などにひそむ歴史を、さまざまな視点から探る。
もっと見る
閉じる
領主が使う呼び名から村人が使う呼び名へ変化したらしい荘園地名、上・下、東・西のつく地名、馬がいたとは限らない「馬場」、「地名が先か・人名が先か」問題、国宝「菅浦文書」に現れる地名を追うことで見えてきた土地利用の変化──。
中世から現代に至るまでの変遷を追うと、地名は必ずその指し示す範囲が人間の必要に応じて変化していることがわかる。平成の大合併で多くの歴史的地名が失われたことに危機感を抱いた著者が、北近江三郡(長浜市・米原市と彦根市北部)の荘園名、大字名、小字名などにひそむ歴史を、さまざまな視点から探る。
目次
はじめに ─地名を知ることの意義─
第一章 荘園と地名
荘園の名が変わること ─「在地方荘園名」の成立─
荘園名の継承 ─荘園名の復活と小地名化─
[コラム]地名から「下」が取られる話
[コラム] 村と方角地名
第二章 地名の諸相
伸縮する地名 ─地名階層から見た歴史学─
「馬場」・「番場」地名考 ─「馬」と無縁な「馬場」地名の話─
琵琶湖の港「朝妻」のたどった歴史
条里制と地名
城郭地名「御館」に関わる歴史
[コラム]小字「サカサマ」は何が逆さま
[コラム]地名が先か、人名が先か
第三章 菅浦と地名
地名を通した中世菅浦の復元
菅浦の田畠と「惣」 ─地名による開発復元─
〈参考〉検注帳・年貢納帳の分析
[コラム]菅浦の淳仁天皇伝説と「這坂」
あとがき
もっと見る
閉じる
第一章 荘園と地名
荘園の名が変わること ─「在地方荘園名」の成立─
荘園名の継承 ─荘園名の復活と小地名化─
[コラム]地名から「下」が取られる話
[コラム] 村と方角地名
第二章 地名の諸相
伸縮する地名 ─地名階層から見た歴史学─
「馬場」・「番場」地名考 ─「馬」と無縁な「馬場」地名の話─
琵琶湖の港「朝妻」のたどった歴史
条里制と地名
城郭地名「御館」に関わる歴史
[コラム]小字「サカサマ」は何が逆さま
[コラム]地名が先か、人名が先か
第三章 菅浦と地名
地名を通した中世菅浦の復元
菅浦の田畠と「惣」 ─地名による開発復元─
〈参考〉検注帳・年貢納帳の分析
[コラム]菅浦の淳仁天皇伝説と「這坂」
あとがき
前書きなど
我々の周りには、多くの地名がある。たとえば、私の住む滋賀県長浜市国友町は、昭和十八年(一九四三)に長浜市が成立する前までは、滋賀県坂田郡神照村大字国友と言っていた。さらに、江戸時代は近江国坂田郡国友村。中世は近江国坂田郡国友荘の一部であった。古代は坂田郡内であったが、郷名が特定できない。
東京へ出かけて、あなたはどこから来たか問われた時、私は滋賀県長浜市から来たと答える。しかし、考えてみれば「滋賀」や「長浜」という地名は、「国友」という地名にとっては、本来無縁な地名なのだ。「長浜」は長浜市が成立する以前は、「国友」の村にとって羽柴(豊臣)秀吉が町を開いた、近くの大きな町に過ぎない。さらに、「滋賀」という地名に至っては、五十キロ以上も離れ、明治初年にたまたま県庁がおかれた大津を含む郡名に過ぎない。それぞれ、市や県ができることにより、その地名が広域化して、本来は関係がない「国友」のような他地域まで含む結果となった訳である。
「地名は生き物だ」ということを、我々は忘れがちである。長期的に見れば、必ず地名はその指し示す範囲が変化する。それも、その土地に住む人間の必要に応じて変わっていくものである。地名の範囲が地域の状況に応じて変化するとしたら、逆にそれを研究することによって、地域の歴史を解明することができるはずである。これが、本書で考えたいことである。
もっと見る
閉じる
東京へ出かけて、あなたはどこから来たか問われた時、私は滋賀県長浜市から来たと答える。しかし、考えてみれば「滋賀」や「長浜」という地名は、「国友」という地名にとっては、本来無縁な地名なのだ。「長浜」は長浜市が成立する以前は、「国友」の村にとって羽柴(豊臣)秀吉が町を開いた、近くの大きな町に過ぎない。さらに、「滋賀」という地名に至っては、五十キロ以上も離れ、明治初年にたまたま県庁がおかれた大津を含む郡名に過ぎない。それぞれ、市や県ができることにより、その地名が広域化して、本来は関係がない「国友」のような他地域まで含む結果となった訳である。
「地名は生き物だ」ということを、我々は忘れがちである。長期的に見れば、必ず地名はその指し示す範囲が変化する。それも、その土地に住む人間の必要に応じて変わっていくものである。地名の範囲が地域の状況に応じて変化するとしたら、逆にそれを研究することによって、地域の歴史を解明することができるはずである。これが、本書で考えたいことである。
著者プロフィール
昭和36年(1961)、東京都世田谷区生まれ。昭和61年3月、明治大学大学院文学研究科(史学専攻)博士前期(修士)課程修了。専攻は、日本中世史・近世史。特に、国宝「菅浦文書」や、戦国大名浅井氏に関する研究を行なう。昭和61年4月から市立長浜城歴史博物館(現在は長浜市長浜城歴史博物館)に学芸員として勤務。担当した展覧会は、特別展『石田三成 第2章─戦国を疾走した秀吉奉行─』(平成12年)、特別展『戦国大名浅井氏と北近江』(平成20年)、NHK大河ドラマ特別展『江~姫たちの戦国~』(平成23年)など多数。著書に『テクノクラート小堀遠州』(サンライズ出版)、『近江が生んだ知将 石田三成』(サンライズ出版)、『浅井長政と姉川合戦』(サンライズ出版)がある。平成23年NHK大河ドラマ「江~姫たちの戦国~」では、時代考証スタッフをつとめた。平成26年4月から、長浜市長浜城歴史博物館の館長を3年間勤める。市民協働部次長を経て、平成30年4月から長浜市市民協働部学芸専門監。
もっと見る
閉じる
担当から一言
準備中
